1. はじめに なぜ今、こんな動きがあるの?
「さいきんSNSで、『財務省の前でデモがあった』と話題になっているけど、本当にそんなことがあったの?」
こう思った人も多いでしょう。
じっさい、2024年の年末から2025年の春にかけて、「財務省デモ」や「財務省解体デモ」とよばれるデモがくり返しおこなわれました。
ばしょは東京・霞が関の財務省前で、参加した人たちは「増税」や「財政政策」に対するふまんや不安をうったえました。
この記事では、「なぜ今、財務省前でデモが起きたのか?」「その根本にあるふまんや不安は何なのか?」「私たちのくらしとどんな関係があるのか?」を、やさしく解説していきます。

2. どうして「財務省デモ」が起きたの?
今回の財務省デモの背景には、政府の経済政策や増税への不安・うたがいの気持ちが強くあります。
「消費税はそのまま」でも、くらしは楽にならない?
2025年はじめ、政府は「消費税率は当面そのまま」と発表しました。
でも、物価がどんどん上がっている中、給料はなかなか増えず、「減税がないと、出費ばかりふえてしまう」と感じる人が多いのが現実です。
とくに「保険料」や「医療費」などが年々高くなっていて、「生活が大変なのに、さらにふたんを増やされるのか?」という声がいっきに広がりました。
さらに「103万円の壁」問題など、働く人たちが日ごろ感じている悩みや不満も、今回のデモが大きくなった理由のひとつです。
3. デモのようすを見てみよう
この財務省デモは、2024年12月から2025年4月にかけて何度もおこなわれました。
とくに2025年4月29日のデモには、主さい者の発表で約2,000人が参加し、メディアでも大きくとり上げられました。
いろいろな人が「わたしの思い」をかかえて
参加者は学生や子育て世代、年金生活の人、会社員など本当にさまざま。
かかげられたスローガンも、「消費税ゼロに!」「財務省は国民の声を聞いて」といった、毎日のくらしに関わるものが中心です。
SNSでひろがる共感とぎろん
X(旧Twitter)では「#財務省デモ」「#増税反対」といったハッシュタグがトレンド入りし、多くの人が写真や動画を投稿しました。
社会的な関心も一時的に高まりましたが、「いきすぎた意見もある」「本当に政策が変わるのか?」といった意見もあり、ぎろんは分かれています。
4. 背景にある「お金の問題」ってなに?
今回の財務省デモの根っこには、「日本の財政はだいじょうぶなのか?」という心配や不安があります。
ここでは、ちょっとむずかしく感じる財政やお金のしくみについて、わかりやすく説明します。
日本政府の借金、1,200ちょう円をこえる
日本は長年、税金だけでは国のよさん(予算)をまかないきれず、「国債(国の借金)」にたよるしかありませんでした。
2025年の時点で、政府が今までにかりているお金の合計は約1,200ちょう円をこえています。
これは、国の年間のお金の動きの2倍以上にもなっています。
家計にたとえると、「毎年の収入より支出が多く、足りない分を借金でうめている状態」です。
高れい化で社会保障費がふえつづけている
さらに日本は、世界でもトップクラスの高れい化社会(お年寄りが多い社会)です。
医療や介護、年金などの「社会保障費」はどんどん増えています。
でも、働く世代(生産年れい人口)はだんだん減っていて、「ささえる人」が減り、「ささえられる人」が増えているので、財政の負担も大きくなっています。
なぜ「減税」を求める声が強いのか?
手取りの給料が減って、物価高もつづき、生活がどんどんきびしくなっています。
だから「減税して、家計の負担をへらしてほしい」「これ以上、ふたんが増えるのは困る」といった声が、今回のデモを大きく動かすきっかけとなったのです。
5. 政府や財務省はどうこたえた?
こうした国民の抗議や不満に、政府や財務省はどのようにこたえたのでしょうか。
財務省のコメント:「安定した財源がひつよう」
2025年5月、財務省の定例会見で、デモについて記者から質問がありました。
財務省の広報担当者は「国民の声は大事にしているが、大きな減税はむずかしい。社会保障を続けるには安定した財源が必要です」とコメント。
これを聞いて、「やっぱり政府は変わらない」「期待はずれだ」と感じた人も多く、ネットでもいろいろな意見があがりました。
今後の動き:「支出改革」に向かう?
政府は2026年度の予算づくりにむけて、「出ていくお金をへらす」「税のしくみを見直す」といった方針を進めようとしています。
また、一部の与党ぎいんからは「生活支援金」や「特定の分野だけでも減税を」といった声も出ていて、これからの政策ぎろんに注目が集まっています。
6. 他の国ではどうしているの?
今回の「財務省デモ」のように、経済政策や増税・減税にたいする市民のデモや抗議は、日本だけでなく世界中で見られます。
ほかの国ではどんなことが起きているのでしょうか?
フランス 年金改革に100万人規模のデモ
2023年、フランスでは政府が「年金をもらう年れいを引き上げる」と発表したことで、大きな反発が起こりました。
デモには100万人以上が参加し、交通機関のストや公共サービスの一時ていしなど、社会全体に大きなえいきょうが出ました。
韓国:若者世代の住宅・しゅうぎょう問題
韓国では、「家が高くて買えない」「仕事が見つからない」といった若い人たちの不満が高まっています。
住宅価格のこうとうや、非正規の仕事がふえたことで、政府への抗議が強くなりました。
こうした声を受けて、一部の政策や支援策が見直されました。
このように、世界の国々でも市民の声が政治やルールを動かすきっかけになっています。
日本でも、声を上げることが会を変える力になります。
7. これからどうなる?私たちにできることは?
2025年春にかけて行われた「財務省デモ」は、ただの一時的な抗議ではなく、「今の社会のしくみや経済政策って、このままでいいの?」という大きな問いかけになっています。
選挙で社会を変えるチャンスも
専門家の中には「こうした市民の動きが、今後の国政選挙に影響をあたえるかもしれない」と指摘する声もあります。
じっさい、いくつかの政党は「消費税の減税」や「金の分け方を見直す」などを公約にかかげていて、市民の関心が政策に反映される可能性も高まっています。
私たちにできるアクション
- 選挙で投票する
- SNSで自分の意見を発信する
- オンライン署名や勉強会に参加する
- 正しい情報をシェアしたり、家族や友だちと話し合う
政治や経済にかかわる方法は「投票」だけではありません。
日ごろのちょっとした行動や関心が、未来を動かす第一歩になるのです。
8. まとめ いっしょに考えていこう
この記事では、2025年の「財務省デモ」をきっかけに、日本経済や財政の問題をわかりやすく紹介してきました。
- 国の借金がふえて、高齢化で財政がくるしくなっている
- 物価高と給料の停滞で、市民の生活はきびしくなっている
- 市民の声が社会を動かす力になることもある
経済政策や税金の問題は、わたしたちの日々の生活と直結しています。
「むずかしいから…」と無関心になるのではなく、まずは知ること・考えることが大切です。
これからの社会をよりよくするために、あなたは何を考え、どんな一歩をふみ出しますか?

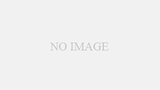
コメント